アメリカ
私が十九歳のとき、母は私にロサンゼルスへの航空券を買ってくれた。
「アメリカでは働きながら大学へいけるそうです。がんばってきなさい」
四十八年前のことである。
ロサンゼルスでは仕事を見つけるのは難しくなかった。
日本人は正直で良く働くとの評価があり、給料の多寡さえ気にしなければ仕事はいくらでもあった。レストランの給仕、給油所での仕事、ぶどう摘み、ペンキ屋と色々な仕事をした。
英語を勉強するために通ったケンブリア・アダルト・スクールは海外からの移民に英語とアメリカ市民としての基礎知識を教えるために設立された学校なのだが、留学生も受け入れていて、あの頃は留学生の方が多かった。
授業料は無料だった。
英語を勉強するのが楽しかった。
夢中で英語を覚えた。ウェブスターの小辞典をいつも持ち歩き、学校の行き帰りのバスの中でも本を読み、わからない言葉があると辞書で調べた。
半年ほどで夢の中でも英語を話すことが多くなった。
見るからに苦学生という感じで粗末な服を着て、勉強に目を輝かせていたあの頃を思うと、自分自身のことながらほほえましくなる。
そんな私に先生方は親切だった。中でもミス・パプキンが私の英語力の充実を我が子の成長を見るように喜んでくれた。

「言葉を大切にしなさい。言葉なくして思考はありえません。思考なくして人格はありえません。良い言葉をたくさん学ぶことは、あなたの人間性を豊かにします」
ミス・パプキンは三十代の独身の女性で、鼻が大きく顔が長く、生徒のなかには不美人と言う人もいたが、私たちひとりひとりに英語の文章をていねいに教えてくれるときの優しい表情は魅力的だった。
良き友にも恵まれた。
ジャンは私より八歳年上で、軍隊に三年いたあと大学に入り、地理を勉強していた。
「名のある学者になってイリノイ州でパン屋をしている母を喜ばせたい」と自分に言い聞かせるように話してくれた。
ジャンが管理人として住んでいるアパートの地下室の部屋に訪ねては話し込んだ。
ジャンは、つたない英語で話す私の人生論に耳をかたむけ、賛同したり反論してくれた。
私がロサンゼルス市立大学に入学した年の夏休みに二人で金を捜しに行った。
アメリカ河の支流の河辺にテントを張った。山を上り谷を下り、砂や土を平なべに入れて水で洗ったり、河にもぐり、河底の砂やじゃりをポンプで吸い上げたりした。
一ヶ月かけても金鉱は見つからず、耳かき四杯ほどの砂金を採集しただけだった。
大金持ちにはなれなかったが、友と二人で夢を追い、夢を語る楽しい一ヶ月だった。
「生まれてきてよかった。このすばらしい人生を心ゆくまで味わってみたい。自分に何ができるか、思いきり試してみたい」
夕食後のたき火の残り火を見ながら二人で語りあった。
二十代の私には人生に終わりがあることが信じられなかった。
いつかは来るであろう老いは遠い先のことだった。青春がいつまでも続き、やりたいことを全部する時間があると思っていた。
半年後にジャンがハワイに行くと言うのでジャンの自動車を百ドルで買った。
物にとらわれない生活をしてみようと思い、一年ばかり車の中で生活をしてみた。 
大学の駐車場で目をさまし、トイレで顔を洗い授業にでる。図書館で勉強をして、夜は自動車を運転してレストランでの仕事に行く。
夕食は仕事先のレストランでお腹いっぱい食べさせてもらえるので朝食と昼食にはお金をかけずにすんだ。近くのスーパーの裏に行くと、それほど傷んでいない果物がただで手に入ることもあった。
大学の勉強はおもしろかった。心理学と化学と英語では「A」をもらった。
アメリカの学生たちにまじって勉強していて英語で「A」をもらったときはうれしかった。
カルフォルニアでは寒い冬がないので着るものにはお金がかからない。何回も洗濯をして青いシャツが空色になり、ズボンのひざに穴があいてもカリフォルニアの明るい空の下ではそれがよく似合う。
靴が嫌いではだしで歩きまわった。ロサンゼルスでもはだしで街中を歩く人は少なかったのだろう。警官に呼びとめられたり、「教室に来るときはせめて何かをはいてくれ」と教師の一人が言うので、それからゴムぞうりをはいた。
アフリカ
大学に入って二年が過ぎた時、ふと思いたって放浪の旅に出た。行ける所まで行ってみようとと思い、六百ドルをポケットに入れ、リュックを背負って出発した。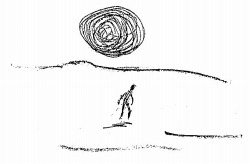
夜は星空を仰いでシュラフで寝て、明るくなると起きて、ヒッチハイクをしたり、鉄道の貨車に乗ったりして四十日ぐらいでニューヨークに着いた。
ニューヨークからは飛行機に乗り、ルクセンブルグに飛んだ。それからドイツに十カ月いて、レストランや肉屋で働いて旅費を稼いだ。
オランダ、ベルギー、フランス、スペインと旅をして、ジブラルタル海峡を渡りアフリカ大陸に入った。モロッコから地中海沿岸を東へ向かった。
旅費が乏しいので、北アフリカでは夜は木陰や岩陰でシュラフに入って寝たが、何日もそんな夜を過ごすと人恋しくなり、アルジェリアではユース・ホステルで二泊した。
そこであったカナダの青年の話しが面白かった。エジプトのピラミッドの頂上で一夜を過ごしたという。
「砂漠の澄んだ空では太陽が落ちると何百もの星がいっぺんに見えてくる。
シュラフにくるまって満天の星空を眺めていると自分がいかに小さいものなのか、砂漠の一粒の砂のように、はかない存在なのかよくわかる」
ピラミッドの上で目を覚ますと地平線から太陽が昇り始めていたそうだ。
朝食のオレンジを食べた時に、オレンジのてっぺんを丸く切って、ピラミッドの上から地平線に向かって投げた。
オレンジ色の小さな円盤は上昇気流にでも乗ったのか、砂漠の上をどこまでも飛んで行った、と遠くを見る目で語った。
カナダの青年と別れ、チュニジア、リビアと旅をしてエジプトに入りギザ地区にたどり着いた。
スフィンクスが虚空を見上げ、幾つものピラミッドが砂の上にそびえていた。
一番大きなクフ王のピラミッドの周りを歩いていると、ラクダを連れた男が寄ってきて、ラクダに乗れと誘った。金はないと言うと、私の身なりを見て納得したようで、何をしているのかと聞く。
ピラミッドに登り易い場所を探しているのだと言うと、ひとつの警告板に連れて行った。
「危険!ピラミッドの登頂を禁ずる。ギザ地区警察署署長」
アラブ語と英語で書いてあった。一年前にアメリカ人の観光客が転落して死亡してからこの警告板が立ったのだそうだ。
日が暮れるのを待った。観光客も物売りもいなくなり、暗がりの中を衛兵がピラミッドとスフィンクスの周りを巡回している。
音をたてないように気を付けながら登り始めた。
ピラミッドは大きな長方形の石を積み重ねて作った百五十メートルぐらいの小山だから、土台の部分は懸垂の要領でよじ上れば良い。
上に行くにつれ石が小さくなり登り易くなる。
まっすぐ上に行くのが難しい場所は横に行き、足がかりの良い個所を選んで登る。
一時間ぐらいで百メートルほどを登ったあと、右へ行っても左へ行っても石の角がぼろぼろに崩れていて先には進めなくなった。よじ上る手がかりも見つからない。
少し降りて新たな路を探そうとしたが、登るより降りる方が難しく、降りる個所はわからなくなっていた。
六十度くらいの傾斜だろう、足を踏み外すと、どこまで落ちるかわからない。
薄闇の中でしばらく思案したが良い考えは思いつかなかった。大声で助けを求めた。
「ヘルプ!ヘルプ!」
アラブ語で何か問いかけていたが、やがて違う男の声で、英語での指示があった。
「ガイドを呼びにやったからそこを動くな」
二時間も待つと上の方から男が一人私の近くまで降りてきた。導いてもらおうと思い手をのばすと、「おれにさわるな」と厳しく叱られた。
ガイドの指示通りに動くと三十分ほどで頂上に着き、そこからは難無く下まで降りていけた。
警察の派出所に連れて行かれ、留置場にでもいれられるかと覚悟をしていたがそれはなく、住所氏名を記帳するだけで済んだ。
ガイドが夜遅くまで開いているレストランに連れて行き、「俺が命を救ってやった日本人だ」と皆に紹介し、夕食を食べさせてくれた。その夜はガイドの家に泊まった。
所持金が十二ドルしか残っていなかったので、旅費を稼ごうと思い仕事を探した。
労働者の余っている国で、いい仕事はなかった。
屑鉄置場での仕事を見つけたが、一日中屑鉄を運んでも夕食代にしかならず、三日働いてやめた。旅費が稼げないので陸路の旅を続けるのはあきらめた。
スエズ運河では東へ向かう船が、通行許可のおりるまで沖で停泊していた。
野菜を売る小舟に乗せてもらい、日本へ行く船を訪ねた。
どんな仕事でもするので日本まで乗せてくれと頼んだが、乗せてくれる船はなかった。
エジプトの人たちは親切だった。
道を歩いていると呼び止めて熱くて甘いチャイを飲ませてくれた。カバブを食べさせてくれる人もいた。
三週間が過ぎ、お金は一ドル札二枚になった。空腹をかかえて運河のふちに座っていると行きかう船がゆがんで見えた。頬に涙がつたわっていた。
「一度だけの人生だったら、もっと勉強がしたい」
この後、私は運よく香港の貨物船に皿洗いとして乗せてもらい日本に帰りついた。
一年間働いた後アメリカに行き、レストランや給油所で働きながらカルフォルニア・ステイト・カレッジで心理学を専攻して卒業した。
自分の人生をふりかえり思う。
勉強は楽しかった。今まで知らなかったことを知り、今までできなかったことが出来るようになるのは楽しかった。
英語の得意な夫と
英語の苦手な妻が作った英会話入門
妻が英語を習いたいと言った。 独身のころラジオの英語番組を聞いたり、英会話教室にも通ったが、長く続かなかったと言う。
「初級クラスでも、よく話せる人が多い。私が一番ダメだった」
妻はきまり悪そうに言った。
英語は苦手だ、でも習いたいと言う。
妻が使えそうな教材はないか二人でさがしたが、これというものがなかった。
妻が必要なのは、英語の基礎からやさしく教えてくれるものだが、教材の多くは学ぶ人がすでに英語をよく知っていると想定していた。
ラジオやテレビの英語番組を聞いてみたが、意外と難しかった。
「本当に初心者向きの英会話教材はないね」
私の仕事は出張が多い。出張先ではひまな時間がある。ワープロを持ち歩き、六ヶ月かけて英会話入門の原稿を書き上げた。それを妻に渡した。
妻は目を輝かせた。
「すごい」
翌日、
「どうだい。君の正直な意見が聞きたいんだ」
「私の正直な意見でいいね」
「ああ」
「むずかしすぎる」
わかりやすく書きなおした。
「どうだい」
「怒らない?」
「ああ、怒らないよ」
「むずかしくないけど、たいくつ」
原稿は本棚にしまった。
一レッスンずつ新たに作り、妻に英語を教えた。
妻が楽しく学べる日もあれば、喜ばない日もあった。
「そうなの、こんなことを習いたかった」
「こんな長い文章は覚えられない」
妻は初心者が何を学びたいか、初心者にとって何が難しすぎるか知っている。私には英語の知識がある。
「二人で初心者むきの英会話入門を作ろうか」
「うれしい。いいよ」
私が書き、二人で読み、書きなおし、ひとつずつレッスンを作り上げていった。
「ABCや曜日の発音も練習したい」
「店の人に声をかけるときはなんて言うの」
「この話は面白くない。省こうよ」
「ひとつの文章に知らない単語がふたつも入っている。書き替えて」
一年半をかけてCD十五巻を作った。英語を習う人と教える人がいっしょに作ったので、本当にやさしい英会話入門ができた。
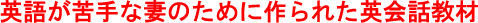
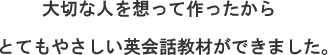
|

